
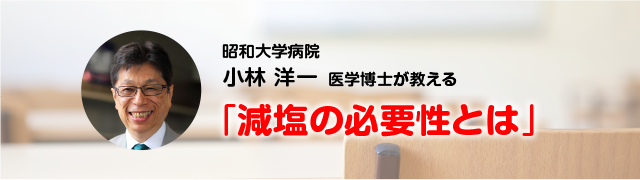
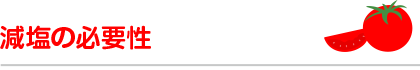
循環器の病気の予防のための研究として、厚生労働省が行っている『ニッポンデータ2010(NIPPON DATA 2010)』があります。この研究によると2010年の高血圧の患者さんの数は4300万人にのぼります。その原因の一翼を担うのは日本人の食塩摂取過多です。減塩1g/日は収縮期血圧1mmHg低下するといわれています。また『健康日本21』では4mmHg収縮期血圧を低下することで脳卒中死亡率を男性8.9%低下、女性5.8%低下し、冠動脈疾患死亡率は男性で5.4%、女性で7.2%低下するとしています。日本人の食塩摂取は年々減少していますが、平成26年国民健康・栄養調査』では一人一日当たり男性10.9g、女性9.2gと、 欧米の高血圧ガイドラインの6g未満には遠く及びません。多くの疫学的研究は食塩過剰摂取が心血管病リスクを増加することが明らかとなっています。特に、減塩は冠動脈リスクに比べ脳卒中リスクを強く抑制することがわかっています。このような理由から、減塩が健康を維持するうえでとても重要であるといえるでしょう。

体内のナトリウムとカリウムはとても重要なミネラルであり、両者は拮抗的に働いています。腎臓ではナトリウムが排泄され再吸収されますが、カリウムはナトリウムの再吸収を抑制して、結果的にナトリウムを排泄し、血圧を下げるように働きます。また、カリウムは心臓の収縮と調律を整えるのに必要で、低くなると不整脈が出やすくなり時には命にかかわることもあります。一方、高値になっても徐脈などの不整脈が出やすくなります。カリウムはトマト、バナナ、リンゴなどの野菜や果物に多く含まれていますので、高血圧の人は積極的にカリウムを摂取することが勧められます。ただし、腎臓病を持っている方、カリウムを保持するお薬を飲まれている方、高齢の方は、主治医の先生に食事のご相談をしていただくことが必要です。

小林 洋一 (こばやし よういち)
昭和大学医学部内科学講座主任・循環器内科学部門 教授
昭和大学病院 副院長・CCU部長・循環器センター長
日本循環器学会(専門医、評議員、関東甲信越地方会評議員)、日本内科学会(評議員、認定医、指導医、関東甲信越地方会評議員)、日本高血圧学会(指導医)、日本不整脈学会(理事、評議員)、日本心電学会(理事)、日本心不全学会(評議員)、日本心臓リハビリテーション学会(理事、評議員)、独立行政法人医薬品医療総合機構専門委員など
