



水の保全
カゴメグループは商品の原料となる作物の栽培に水を使い、加工段階でも多くの水を使用しています。日本は水が比較的豊かといわれていますが、世界では水不足が深刻な地域が存在しています。そのため、水への負荷をできる限り小さくすることが必要です。これに対し、カゴメグループは、活動する地域の水資源を守るため、国内6工場、海外7工場で水管理計画を策定し、取水量・排水量、水リサイクル量、排水の水質等を管理して、それぞれの地域に合ったサステナブルな対応を進めています。
カゴメグループ 水の方針
1. カゴメグループおよび主要サプライヤーでの水リスクを把握します
2. 地域の水資源を守るため、取水量の削減に努め、水を大切に使用します
3. 使用した水は、きれいにして地域に還します
4. 水リスクの高い事業所においては、その地域に合った水の対策を推進します
目標
| 区分 | 課題 | 2025年のKPI | |
| 3.水の保全 | 1)国内工場の取水量の削減 | 取水量の毎年1%削減(生産量あたり) |
原単位を4%削減 (2021年比) |
|---|---|---|---|
| 2)水の浄化と循環利用の推進 | 地域の排水基準の順守 | 排水基準順守 | |
|
3)高リスク拠点への対応 (主要サプライヤー) |
主要サプライヤーの実態調査と対策実施 | 高リスク拠点の対策決定 | |
主な取り組み
国内工場の取水量の削減
水使用量の削減(効率的な水利用・再利用の促進)
カゴメグループの工場では、原料農産物の洗浄や製品の冷却などで大量の水を使用していることから、効率的な水利用や再利用などを促進し、水使用量の削減に努めています。国内工場では生産量あたりの取水量を毎年1%削減することを目標としています。2023年度は前年比0.6%の削減となりました。
今後も使用方法の再点検や冷却水の再利用などを通じて水使用量の削減に努めます。
水の浄化と循環利用の推進
水質保全
各工場には排水処理施設を設置し、工場内で使用した水は法律で定められた基準に基づき、きれいな状態にして河川に放流することで地域に還しています。また、工場が所在する地域に水質保全のための条例がある場合は、その基準を順守し、その水域の環境保全に努めています。
2023年度は、水質(量)に関する許可・基準・規制など、環境に影響する重大な事故および違反はなく、罰金および処罰に関するコストは発生していません。
高リスク拠点への対応
水リスクの把握
カゴメグループは、商品の原料となる作物の栽培に水を使い、加工段階でも多くの水を使用しているため、水の負荷をできる限り小さくすることが必要であり、国内6工場と海外7工場を対象に水リスク評価を行っています。なお、国内6工場は、AqueductのBaseline Water Stressで水関連リスクが高くないことから、海外工場に注力しリスク評価を行いました。水リスク評価は、流域のリスクと操業リスクをそれぞれ5段階(1~5)で評価し2次元マトリクス化し、優先拠点を特定しています。
【流域リスク】
流域リスクは、「水資源リスク」、「水量に関する評判リスク」、「水量に関する規制リスク」、「渇水リスク」、「水害リスク」、「水質リスク」、「水質に関する評判リスク」、「水質に関する評判リスク」を、世界各地の拠点に対して同一の基準で水リスクが評価できるAqueductおよびWater risk Filterの該当する指標を用いて調査しました。
なお、AqueductおよびWater risk Filterは、精度に限界があり実態に即していない可能性があるため、社内アンケート調査にて流域リスク結果を補正し、評価の妥当性について社外コンサルタントを用いて確認しています。
【オペレーショナルリスク】
オペレーショナルリスクは、水に関連する事業の特性を水リスクに反映するため、「水源別の年間取水量」や「放流先別の年間排水量」、「年間売上」などの情報を収集し、相対的に評価しています。また社内アンケート調査にて拠点独自の事業情報を収集し、評価の妥当性について社外コンサルタントを用いて確認しています。
これらの水リスク評価の結果、ポルトガルのItalagro社、FIT社は、地域の水資源や水質等 に関するリスクが高くカゴメグループの中で取水量・排水量が多いこと、オーストラリアのKagome Australia Pty Ltd.は、渇水や水害による調達への影響の実績があり、これらのリスクが高いことから、水リスクが高い優先拠点と特定しました。これら2カ国3工場はカゴメグループ全体の取水量のおよそ半分を占めるため、本拠点でのリスク対策は重要と考えています(水リスクの高い優先拠点の水使用状況はESGデータブックに掲載)。
水リスクへの対策
水リスクが高い優先拠点においては、カゴメグループの各海外工場と現地関係者等でエンゲージメントを行い、各工場や地域に応じたさまざまな対策を講じています。
① ポルトガルのItalagro社の事例
カゴメグループ最大規模の水使用工場での取水量削減取り組み
カゴメの連結子会社であるItalagro社は、カゴメグループの工場の中で最も取水量が多いため、水使用量の削減が特に重要です。
そのため、トマトの濃縮機や殺菌機などから発生する蒸気を回収してボイラー水として再利用しています。
また2023年からはクーリングタワーを設置し、工程で使用した水を冷却水として再利用しています。2024年以降、更にクーリングタワーを増設し、取水量の削減を目指します。

Italagro社の温水の回収タンク
② オーストラリアのKagome Australia Pty Ltd.の事例
カゴメの連結子会社であるKagome Australia Pty Ltd.(オーストラリア、ビクトリア州)は、2017年に4月の大雨等でトマト栽培に大きな被害を受けました。過去のデータを調査した結果、4月後半に大雨のリスクが高いことから、2018年からリスクの高い時期を避けてトマト栽培を行うなどのリスク回避を図っています。
大雨リスクに備えた砂地でのトマト栽培試験
降水量が多い場合、粘土質土壌では収穫機が畑に入れず収穫できない恐れがあるため、排水のよい砂地の人参用の畑を使いトマトを栽培する試験を2022年、2023年に行いました。今後も課題を解決し、砂地でのトマト栽培の実現を目指します。
工場で使用した水のダムへの貯水と近隣農家への提供
オーストラリアでは、大雨とは逆に干ばつのリスクもあるため、冬に工場で使用した水をダムに貯水し、春に近隣農家に提供し、水の再利用にも努めています。

Kagome Australia Pty Ltd.の砂地でのトマト栽培試験
③ アメリカのIngomar Packing Company, LLCの事例
トマト由来の再利用水の地域への提供
カゴメの連結子会社であるIngomar Packing Company, LLC(以下、インゴマー)の周辺地域※は、地下水の枯渇、干ばつ時の水の供給制限などに悩まされています。この問題に対応するため、インゴマーは、Botanical Water Technology (BWT) の特許取得済みの設備(Water Harvesting Unit(WHU))を設置しました。WHUを設置したことで、2022年8月から、トマトを蒸発濃縮してトマトペーストを製造する際に発生し廃棄されていた蒸発凝縮水を回収し、飲用できるレベルまで精製し、植物由来の純水(Botanical Water)として再利用することが可能となりました。
2022年は、精製した水120万Lを中央カリフォルニア灌漑地区(CCID)に提供しました。2023年には、カリフォルニア州公衆衛生局(CDPH)から、この植物由来の水の販売許可を取得しており、現在、第三者への提供を検討しています。
※カリフォルニア州の重要な水源であるサンワーキン川流域
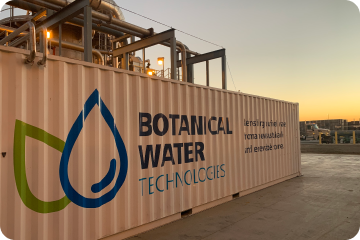
④ 最小の水で収穫量の最大化を図るトマト栽培システムの開発(NEC社との協働)
スマートアグリ事業の推進
カゴメの連結子会社があるポルトガルの試験圃場において2015年3月から、日本電気株式会社(NEC)と共同でAIとリモートセンシング技術を活用した最先端の加工用トマト栽培技術の開発を進めてきました。具体的には、熟練者の肥培・灌漑管理手法をAIに学ばせ、それと圃場に設置した気象・土壌などの各種センサの情報と人工衛星から得られるリアルタイムのトマトの植生情報を組み合わせて、最小限の水・肥料などの使用で収穫量の最大化を図るものです。この技術により、農業の効率化と環境負荷の極小化を目指しています。
利用者は、タブレットやスマートフォンを使い、圃場全体の生育状況やストレス分布をリアルタイムに把握でき、収穫日や収穫量、天候や病害リスクが予測できるようになるとともに、AIが導き出した最適な肥培・灌漑管理手法を参照することができます。
これまでにポルトガル、スペイン、オーストラリア等の地域で実証試験や事業検証を進め、2022年9月、ポルトガルに新会社DXAS Agricultural Technology Ldaを設立し、加工用トマト農家や事業者向けのサービスとして本格的な事業展開を進めています。

水に関連する環境保全コスト
環境会計にて開示している環境保全コストのうち、2023年の水に関連するコストは以下などに費用を投入し75百万円でした。
●排水処理能力の増強、曝気槽躯体補修工事、排水処理場の生ごみ処理機の導入など










