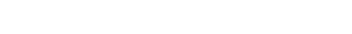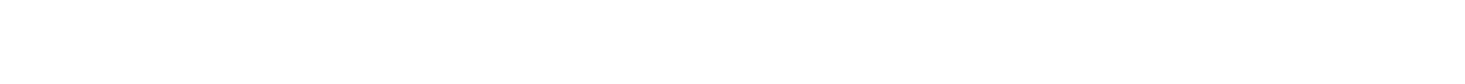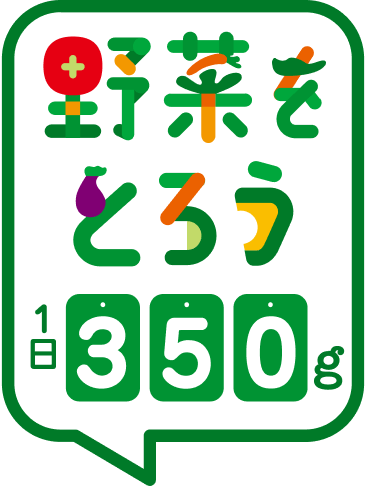日本の野菜不足解消に取り組む「野菜をとろうキャンペーン」は、今後もますます加速していきます
2020年1月に開始した「野菜をとろうキャンペーン」では、これまでに多くの企業や団体とも共創しながら様々な施策を行なってきました。「1日350g」の野菜摂取目標実現へ向けて、カゴメが果たすべき役割は何か。また、様々な企業・団体と共創しながら進める「野菜摂取推進プロジェクト」の現在地とは?
カゴメ株式会社 代表取締役社長 山口聡が語ります。
──改めて「野菜をとろうキャンペーン」とは?
「野菜をとろうキャンペーン」は、厚生労働省が推奨する(※1)「1日350g」の野菜摂取を実現することで、健康寿命延伸、ひいては農業振興・地方創生、持続的な地球環境といった社会課題の解決を図ろうとする取り組みです。
「野菜をとることは大事」、これは多くの人が認識するところだと思います。実際に、健康寿命を損なう生活習慣病の予防や症状の改善に野菜の栄養素が密接に関係していると考えられる多くのデータがあります。
それにも関わらず日本人の平均野菜摂取量はここ十数年間ほとんど変化しておらず、野菜不足の状態が続いてしまっています(※2)。この状況を考えると「1日350g」実現のためには社会全体に「野菜をとろう!」という大きな流れをつくっていくことが必要であり、そのためにはできる限り多くの人と協力し合うことが不可欠だと考えています。
「野菜をとろうキャンペーン」は、そうした社会的な流れをつくり出し、日本の野菜不足を解消しようとする活動なのです。
※1:「厚生労働省 健康日本21」が推奨する1日の野菜摂取目標量は350g
※2:平成22年~令和元年国民健康・栄養調査(厚生労働省)での日本人の平均野菜摂取量は約290g
──キャンペーンにおける「野菜摂取推進プロジェクト」の役割と成果とは。
「野菜をとろうキャンペーン」の役割として「①野菜不足を自覚してもらう ②なぜ野菜が必要なのか理解してもらう ③おいしく上手なとり方を知ってもらう」ことが重要だと考えており、そのための施策を複数行なっています。その一例が、カゴメがドイツのメーカーと共同開発した、野菜の摂取量を計測する機器「べジチェック®」の普及活動による新たなタッチポイントづくりや、カゴメオリジナルの「野菜マエストロ検定」で当社社員を野菜の魅力の伝道師へと育成する取り組みです。
そして「野菜をとろうキャンペーン」に賛同いただける企業・団体を繋ぎ、ひとつのプロジェクトとして実効性のある施策を次々と打ち出しているのが「野菜摂取推進プロジェクト」になります。
健康寿命延伸、農業振興・地方創生、持続的な地球環境といった社会課題にアプローチするためには、カゴメ一社の力では限界があります。「野菜摂取推進プロジェクト」は様々な企業・団体の知見を結集し、オープンイノベーションによって大きな力を生もうとする活動なのです。
実際にプロジェクトを通じて実に多種多様な業界、企業・団体間の連携が実現しており、カゴメ単独ではアプローチしにくいお客様との接点をつくることができています。
──キャンペーン開始から4年が経ち、当初からの変化や見えてきたことは?

ここまでの4年間で多くの施策が生まれてきました。キャンペーン開始前には持っていなかった生活者とのタッチポイントが生まれている点、また企業の枠組みを超えた取り組みが生まれている点は大きな変化であり、成果であると感じています。
これまでの主な施策を振り返ってみましょう(※以下の各数値は2023年12月時点のもの)。
「べジチェック®」レンタル・リース件数延べ1500台以上、計測回数累計660万回以上
手のひらをセンサーに数十秒当てるだけで野菜の摂取量が足りているかを計測できる機器「べジチェック®」。健康経営に積極的な企業や、各種イベント、スーパーマーケットなどへの設置を進めてきましたが、おかげさまで累計計測回数は660万回以上と普及が進んでいます。


「野菜マエストロ検定」(社内検定)取得1600人
 ステークホルダーや生活者に野菜の魅力を伝えられるよう、社員一人一人が野菜に関する様々な知識を身につけるべく誕生した「野菜マエストロ検定」 。これまでに延べ1600人以上の野菜マエストロが誕生しました。
ステークホルダーや生活者に野菜の魅力を伝えられるよう、社員一人一人が野菜に関する様々な知識を身につけるべく誕生した「野菜マエストロ検定」 。これまでに延べ1600人以上の野菜マエストロが誕生しました。
「カゴメ野菜生活ファーム富士見」来館者数延べ14万人を突破
野菜のことが大好きになる体験型の“野菜のテーマパーク”として2019年にオープンした「カゴメ野菜生活ファーム富士見」。農業体験や調理体験、最新の技術を使った工場見学などのコンテンツを用意しており、おかげさまで延べ14万人に来館いただくことができました。


「野菜摂取推進プロジェクト」賛同社数19社/施策数累計113企画
プロジェクトの賛同企業は現在19社。各事業領域におけるトップランナーたちが集い、それぞれの得意分野・強みを生かしながらこれまで数多くの共同企画を行ってきました。のべ、情報発信は7800万人、7万人に直接体験してもらう機会を創出できました。

なお「野菜摂取推進プロジェクト」からはユニークな企画が複数生まれています。
例えばヤンマーマルシェ株式会社・タキイ種苗株式会社との共同企画では、トマトの植え付けから栽培、収穫、調理して食べるまでを一貫して行う体験イベント「植育からはじまる食育」を企画しました。のべ約60名にご参加いただき大盛況のイベントになりましたが、私が特に意義を感じたのは、参加前は「トマト嫌い」だったという女の子がトマトをたっぷり使ったスパゲティをパクパクと食べ、イベント終了時には「美味しかったし、楽しかった」と目を輝かせてくれたことでした。

「1日350g」達成に向けては、こういった“小さいけれど確かな一歩”の積み重ねが大切なのだと思っています。
他にも「野菜摂取を促進することで、健康寿命を延ばす」という大きな目標を共有することで、想像以上の取り組みに繋がった事例がいくつも生まれました。これからも本プロジェクトを通じて着実に生活者のみなさまとのタッチポイントを増やしながら、“想像を超える化学変化”が生まれることも楽しみにしたいと思います。
──「1日350g」実現に向けたこれからのカゴメの取り組みと、「野菜摂取推進プロジェクト」が目指す姿とは

生活者のみなさまに分かりやすく丁寧に野菜をとることの大切さを伝え続けること、その上で魅力的なコンテンツやプロダクトを提案し、実際に行動してもらうことが重要だと思っています。
そのための施策としては「べジチェック®」をキーコンテンツとして野菜不足の気づきとなる体験を提供したり、トマト苗栽培に関するコンテンツの拡充や体験型イベントを開催するなど生活者のみなさまとの接点を広げていく動きを続けながら、オープンイノベーションによる新しいアウトプットの創出にも積極的にチャレンジします。
また、どのようにしたら生活者のみなさまに野菜をもっと手軽に摂取していただけるかを考え発信することも大事だと考えています。 例えば野菜摂取の方法はサラダだけではありません。加熱調理をしたり加工品をうまく活用するなど、生活者の様々なライフスタイルのなかで上手に取り入れられる方法を伝え続けていきたいと思います。
そしてこうした取り組みをする上で「野菜摂取推進プロジェクト」は非常に重要で、ますます貴重な場になってきます。
おかげさまで現在「野菜摂取推進プロジェクト」には、様々な領域におけるトップランナーたちに参画していただいています。それぞれの強みを発揮し合うことができれば、「日本の健康寿命を延伸する」という目標達成に向けた強力なエンジンになるはずです。カゴメはプロジェクトの発起人として、ご参画いただいている企業・団体間の協業・コラボレーション機会創出に努めてまいります。
本プロジェクトを通じて、生活者のみなさまが「楽しみながら、おいしく野菜を摂取できる」機会を増やしていきたいと思います。