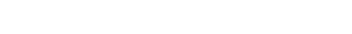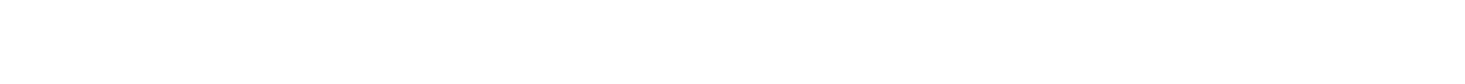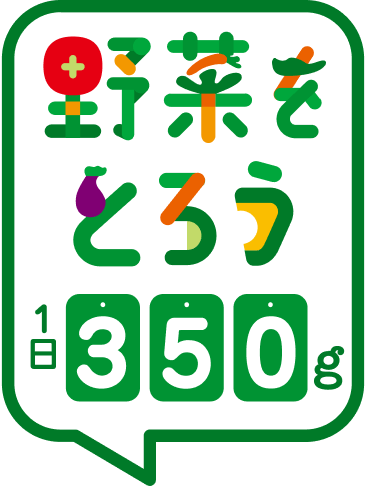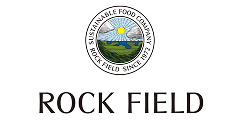地域に根差した取り組みを通じて、社会の「幸せ」に貢献したい
愛知・岐阜を基盤に交通や不動産など地域を支えるサービスを提供する名古屋鉄道が、2024年4月に野菜摂取推進プロジェクトに参画しました。野菜摂取を推進することが、名古屋鉄道が考える魅力的な地域づくりにどのように繋がるのか。同社代表取締役社長・髙﨑 裕樹さんに聞きました。
地域生活者の健康な暮らしを応援し、地域全体の「幸せ」の総量を増やしたいという思いから、プロジェクトに賛同いたしました。 私たち名古屋鉄道は主な事業エリアと地域経済圏とがほぼ同一という稀有な私鉄会社です。地域に対する責任は非常に大きく、事業を通じて誰もが「行ってみたい」「働きたい」「住みたい」と思える地域をつくっていく必要があると考えています。 地域交通を確実に支えながら、都心部や沿線地域の不動産開発などを積極的に行い地域全体の魅力を引き上げていく動きを今後ますます加速したいと思っていますが、その前提となっているのが「地域生活者や働き手たちを幸せにしたい」という想いです。 「野菜摂取推進プロジェクト」を通じて野菜摂取量を引き上げ、ひいては健康寿命を延ばすことは、地域の「幸せ」に通ずると思っています。
山口社長とのご面談時に伺ったのですが、愛知県はなんと、野菜摂取量日本最下位だそうです。(※)。 聞いた時には「農業県なのになぜ?」と驚きました。私自身も特に野菜不足だという認識はなかったのですが、カゴメさんの「ベジチェック®(野菜摂取量を測る装置)」をやってみると、想像以上に不足していることがわかりました。 カゴメさんの分析によると、この結果には愛知県の外食習慣や「名古屋めし」「モーニング」といった食文化が関連しているかもしれないとのこと。つまり、地域の野菜摂取量を底上げしていくためには食文化そのものをアップデートしていく必要があるということかもしれません。 (※)調査について詳しくはこちらのページをご覧ください 名古屋鉄道は鉄道や不動産を中心に暮らしや観光を支える事業を幅広く行っていますので、私たちが「媒体」となり、さまざまな形で地域全体にメッセージを伝えていくことができると思っています。 ジャストアイディアですが、例えば鉄道駅で「フレッシュ野菜ジューススタンド」を展開したり、私たちが運営するショップでカゴメさんやプロジェクト賛同企業とコラボレーションした商品を販売するなどの取り組みができるかもしれません。 また地域に広がる野菜畑を一つの観光資源として捉えれば、その生産風景を活かして地域生活者や観光客向けの新企画をつくったり、収穫体験を通じて野菜に触れる機会を提供したりといったことも考えられます。 同じ地域に基盤を持つ企業同士、カゴメさんと力を合わせて、愛知県を野菜摂取量日本一にするチャレンジをしていきたいですね。 私たちは地域生活者や働き手を健康に幸せにしていきたい、という企業なので、プロジェクト賛同各社との接点を活かして地域の魅力や付加価値づくりにつながる取り組みをやっていきたいと考えています。 プロジェクト賛同企業のみならず地域企業全体を巻き込んで、健康寿命延伸に取り組んでいけたら良いですよね。企業同士が広くつながって、「健康経営プロジェクト」のようなものに発展していけば地域全体、ひいては日本全体に「幸せ」を拡げていけるかもしれません。 野菜摂取推進プロジェクトにはこれまで接点がなかった企業も多く賛同されているので、それぞれの知見や地域基盤も活かしながら、日本の健康寿命延伸につながる新しいチャレンジをしていきたいですね。地域の野菜摂取量を増やし、地域に暮らす人たちの健康や幸せに貢献したい

──あらためて、「野菜摂取推進プロジェクト」にご賛同いただいたのにはどのような背景があったのでしょうか?
愛知県の野菜摂取量「最下位」から「一位」を目指して挑戦

──愛知県は日本有数の野菜産出額を誇る地域ですが、野菜摂取量はどうなのでしょうか?
──腰を据えて取り組む必要がありそうです。何か具体的なプランはありますか?
プロジェクトを通じて、魅力的な地域づくりを加速する「新たな付加価値」をつくり出す

──本プロジェクトに対してのご期待や、今後「こんなことができたら面白い」といった考えがあれば教えてください。