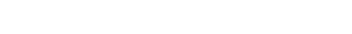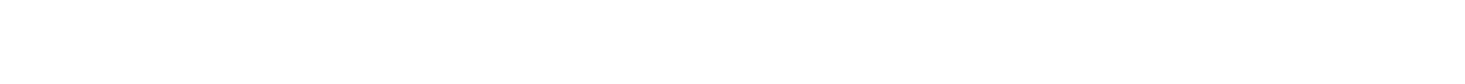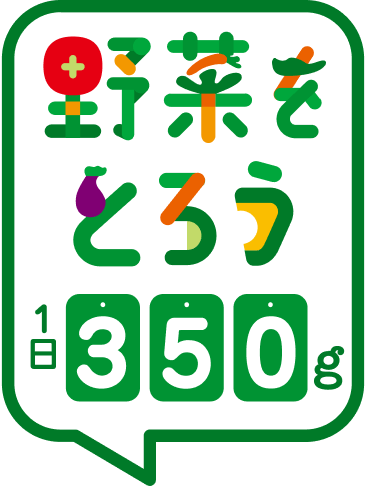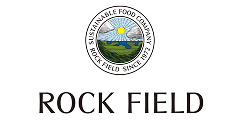地域に根差した活動を積み重ね、健康寿命の延伸に寄与したい
“City as a Service”構想のもと、生活者一人ひとりがWell-Beingを実現できるまちづくりを推進している東急。『「食」とウェルネス、健康寿命』に取り組む思いと、本プロジェクトに参加することで社員やお客様にどのような変化があったかを伺いました。 プロジェクトを通じて、沿線の皆様の健康に寄与できればという思いで参加させていただきました。 そして野菜摂取推進プロジェクトはまさに、野菜をとることを通じて「健康寿命の延伸」を目指す取組みです。沿線の皆様や、多くの生活者の皆様の健康に寄与することができると考えて参加いたしました。プロジェクトの中で、東急にはないサービスやプロダクトを持った企業とコラボレーションの機会が持てるということも魅力的でした。 東急㈱グループが運営する高齢者向け住宅で実施した「野菜講座」で、健康意識の高まりを体感することができたことです。 東急㈱グループは介護領域にも取り組んでおり、その一施設としてサービス付き高齢者向け住宅「ウェリナ旗の台」を運営しております。その入居者様に向けて、カゴメさんに野菜講座をしていただきました。 ご入居者様たちは元々健康に関心の高い方が多いのですが、野菜を摂ろうという意識があっても「量が食べられない」「硬い」などの悩みをお持ちでした。そこで野菜講座では、野菜は温めると嵩が減って食べやすいことや、トマトジュースが飲みやすくなるアレンジ方法など、実践しやすい様々な方法を教えていただきました。野菜という身近な食材に関して「新しい知識を得る」ということにも喜びを感じていただいたようで、その点でも非常に良い機会でした。 そうですね。例えば、ご入居者様に「運動をしましょう」とお誘いしてもなかなかフィットネスルームにいらっしゃいません。そこで、セミナーを開催してお体の仕組みや落ちやすい筋肉などをお伝えすると、そこを強化しようと運動しに来られる方が増えるんですよね。それに似ているかもしれません。 「野菜」はとても身近な題材なので、健康増進を自分ごととして捉えていただくためには最適だと思います。実際にご入居様が、遊びに来られたお孫さんたちに「野菜講座」で知った野菜の話をする場面も見ております。また講座に参加したスタッフから講座に参加できなかったご入居者様に「野菜には骨がないのになぜ倒れない?」といったクイズを出す場面もあったりと、施設全体として健康増進意識の高まりを感じています。 「ウェリナ旗の台」では、引き続き野菜を題材として施設全体のコミュニケーションを活性化するような取り組みができるといいと思っています。例えば、野菜をご入居者様自身が育てて食べるような取り組みもいいですね。 東急㈱グループとしては、東急の施設を使って生活者や地域のコミュニケーションを活性化する体験イベントができるといいなと思っています。地域を緩やかに繋げていくような活動ができるといいですね。 「野菜」は生活者にとってとても身近なので、様々な施策で相乗効果を生みやすいと考えています。 今後はグループで運営する施設間のコミュニケーションも活性化するようなイベント作りをしていきたいです。またカゴメさんとの野菜講座のように、プロジェクト賛同企業と一緒に地域に根付いた啓蒙活動を進めていくことで健康寿命を延伸し、より平均寿命との差が小さくなるように取り組んでいきたいですね。プロジェクトで「健康寿命延伸」を推進し、活気ある沿線づくりに寄与したい

──あらためて、「野菜摂取推進プロジェクト」にご賛同いただいたのにはどのような背景があったのでしょうか?
東急㈱グループは2019年に長期経営構想を策定し、重要テーマとして「Well-being(人生100年時代の安心・安全と、自分らしい生き方を実現できるまちづくり)」を掲げています。活気のある沿線を作っていく上でも、沿線にお住まいの皆様に健康でいていただくことは大事ですので、「健康寿命の延伸」を積極的に推進していきます。健康意識を高めるためには、自分ごと化できる“きっかけ”が大事

──プロジェクトを通じて、印象的だった出来事はありますか?
──「健康になりましょう」と呼びかけるだけではなく、行動に移す方法を伝えることが大事なのですね。
協業を通じて“まちづくり”事業の可能性を実感。地域コミュニケーション活性化を通じて、健康寿命延伸を図りたい

──最後に、これまでの活動を通じての学びや「1日350g」実現に向けてこれから取り組んでみたい活動のアイデアがあれば教えてください。
──「野菜」を使って、コミュニケーションのきっかけを提供していくということですね。
実際にプロジェクトを通じてカゴメさんと、東急が運営する「ネクサスチャレンジパーク早野」で、沿線にお住まいの方々とトマトの苗を植え、育て、食べるという取組みもしております。子どもたちが土にさわり、自分で作ったものを食べるという「“植育”からはじまる“食育”」の実践であり、地域に根差した体験作りです。このイベントがきっかけで「まちづくり」という事業の幅の広さや制限のなさに改めて気がつき、会社や事業の無限の可能性を感じることができました。