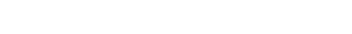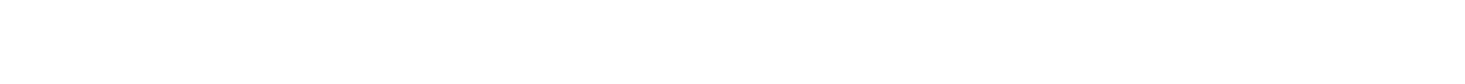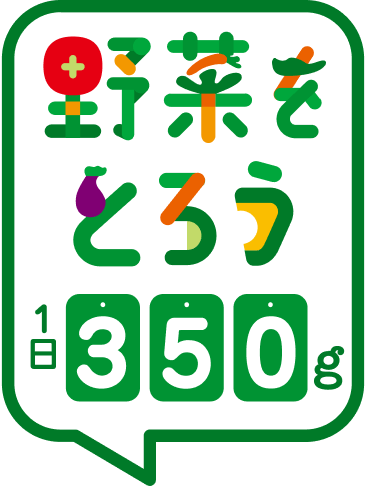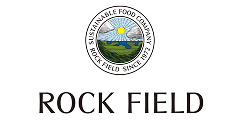知見を持ち寄り、「野菜のおいしさ」を知っていただくための取組みを加速したい
生産者と消費者の懸け橋となり、「食と農」を未来へつなぐことを掲げる全農。生産現場から販売まで、国産農産物の流通過程に幅広く関わるからこそ抱く、野菜摂取推進にかける思い、そして特に若い世代に向けた取り組み内容について教えてもらいました。 異業種企業の知見を借りながら「野菜のおいしさ」を様々な形で表現し、発信・提案していきたいと考えたためです。 日本ではかなり以前から、農林水産省が主体となって食料自給率を上げることや、野菜を食べることを推奨していますが、現状はなかなかうまくいっていません。消費者の方たちは食料自給率を上げるために野菜を食べているわけではないのでアプローチは難しいですし、「野菜を食べよう」とただ呼びかけるだけでは伝わりづらいところがあります。 まずは実際に食べてもらい、野菜をおいしいと思ってもらいたい。そのためのアイデアを異業種の方からお借りできればと思い、本プロジェクトに参加しました。 野菜のおいしさの表現や発信・提案の仕方など、できる工夫は沢山あるはずです。 例えば「野菜+レシピ+調理のための商品」を組み合わせて、店頭の青果売り場で提案するようなことが考えられます。青果売り場はだいたい小売店の入り口付近にあるので、そこを舞台に訴求力のあるコラボレーションをすることで、面白い提案・発信ができるはずです。 2021年8月に、群馬県産の夏秋なすの消費喚起のため、カゴメさんのパスタソース「アンナマンマ トマト&ガーリック」を使った“なすとベーコンのトマトスパゲティ”のレシピやメニュー画像をパッケージにつけて首都圏を中心に販売しましたが、これはとても好評でしたね。 このような「野菜+レシピ+α」の提案力をさらに磨くことで、野菜流通の課題解決にも貢献できるかもしれません。 そういう時には、瞬間的に消費拡大を狙うレシピ提案をSNSや店頭POPなどで仕掛けます。キャベツの収穫が重なってしまった時に、キャベツ1玉をただ「食べてください」と売り場に置くのではなく、レシピの提案をセットで行い消費拡大してもらおうとするわけですが、そこにさらに「簡単においしく食べる」ための商品をセットにして売り場をつくれば、さらに消費者の需要を喚起することができるはずです。 野菜の生産現場での一番の課題は、近年あまりにも高くなった生産コストが、価格に反映できていないことです。野菜の生産自体が大変になっており、このままだと作り手がいなくなってしまうほどです。 生産現場を守るためには野菜を安く売らない、つまり適正価格で販売する方針にシフトしなくてはならない。特に30~40代の若い世代の方たちには、値段という指標だけでなく、納得感をもって購入していただくことが次の消費、そして未来に繋がっていくと考えています。 また消費者の方たちの間にも「なるべく食品の廃棄を減らしたい」といった想いが増えてきているので、そうしたニーズに合うような展開も進めていきます。 なかでも、お子さんがいらっしゃる世代を巻き込むことは非常に大事だと考えています。 私たちはおいしい野菜を届ける。そして野菜を食べた子どもたちの「おいしい」から自然とその家庭の野菜摂取が推進されると、良いですよね。異業種と協業して、野菜の「おいしさ」の表現・発信方法を追求したい

──あらためて、「野菜摂取推進プロジェクト」にご賛同いただいたのにはどのような背景があったのでしょうか?
そんな背景や、私自身が現場で販売に携わってきた経験から、野菜摂取量を増やすためには何よりも「おいしさ」を野菜に感じてもらうことが大事だと考えています。食べてみておいしければ、次の消費に繋がっていきますよね。――ポイントになるのは「おいしく」という部分なんですね。
また、野菜が消費者に届くまでには、生産し店頭に並べるだけではなく「貯蔵・調理」というステップがありますよね。野菜摂取目標量の1日350gを“おいしく”食べてもらえるように、特に貯蔵・調理に関して他業種の方たちと協力し、工夫しながら取組みを進めていきたいと考えています。華やかな売り場作りや魅力的な提案を通じて、野菜はもっと消費者に受け入れてもらえるはず

──実際に、どのような異業種との取り組みが考えられるでしょうか?
──カゴメとのコラボレーションもありましたよね。
日本は南北に長いため、各地域で計画的に植え付けを行うことで、野菜の収穫時期をコントロールすることができます。計画通りのタイミングで収穫できればまんべんなく市場に出荷することができるのですが、最近では猛暑や大雨などの影響で狙い通りにいかず、結果的に収穫が同じ時期に重なる…ということもあります。産地の想いを発信することで、持続可能な農の未来をつくりたい
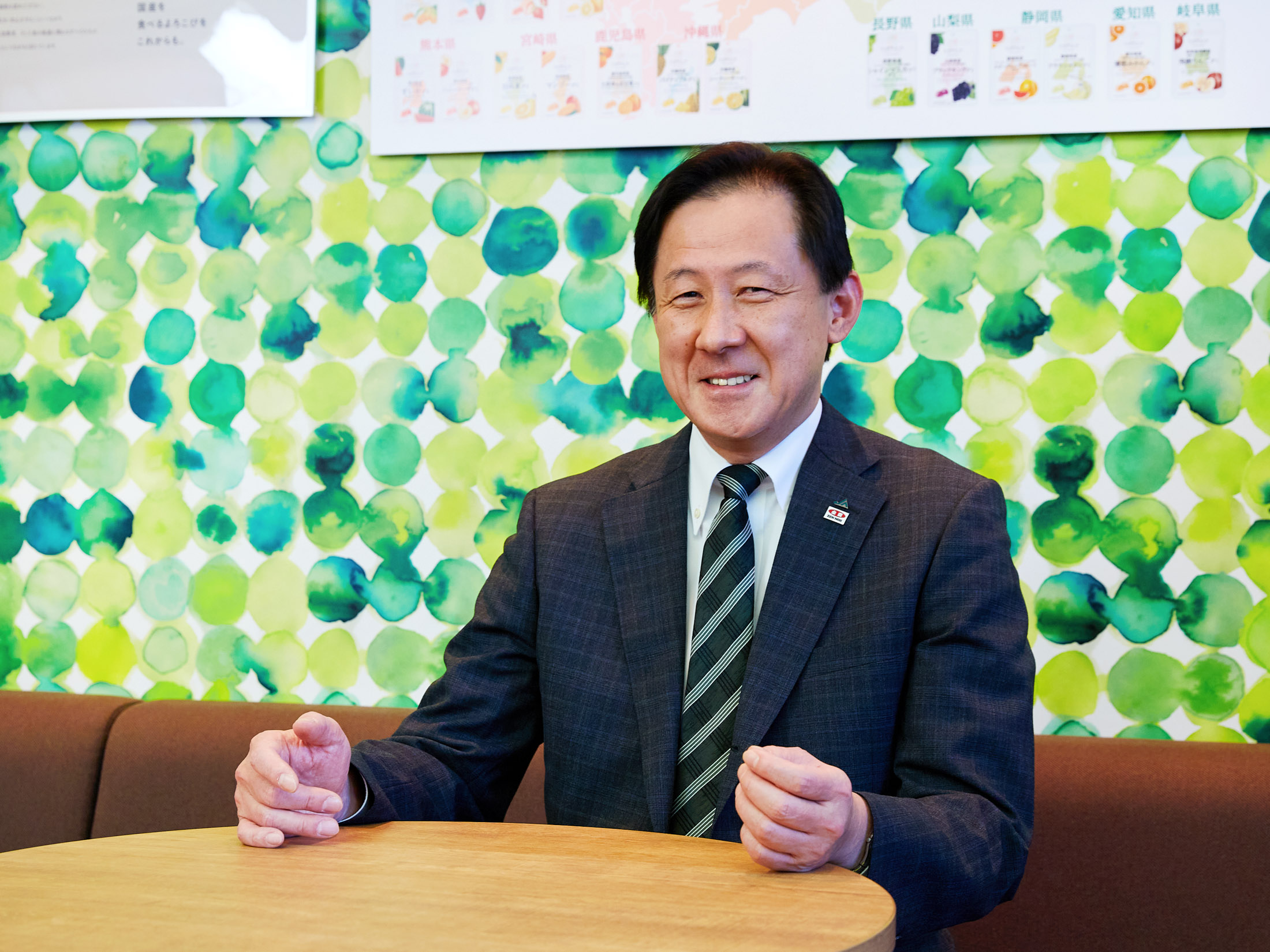
──食と農を未来へつなぐために、解決すべき課題にはどのようなものがありますか?
そのために今力を入れているのは、産地の想いをしっかりと消費者に届けることです。同じ野菜でも、北海道から九州地方まで旬の時期も異なりますし、育て方も異なります。年中スーパーに並んでいる野菜でも、時期によって中身が少しずつ違うのです。生産者のインタビュー動画や店頭POPを作成し、その思いを伝えていこうと思います。――野菜消費を促すためには若い世代がキーポイントになるんですね。
子どもたちの反応というのは実に素直で、おいしい、おいしくないと忖度なくはっきり言ってくれます。そして、子どもが「おいしい」「これ買って!」と言ってくれれば、特に野菜に関する商品の場合、親御さんは買ってくれることが多いですよね。